第三話 ふくらむ何か
「嫌だ。」
零は、即答した。
「零!」
母が困ったような怒ったような、とにかく不機嫌な顔で零を睨む。
だが睨まれようが憎まれ口を叩かれようが、零は絶対に首を縦には振らないと心に決めていた。
夜会なんて、絶対に出るもんか。
母は、零に今夜の夜会に出ろと言う。
零とて、昴という一国の王子であるからには夜会に出席した事がないわけではない。
だが、零には夜会にいい思い出が一欠けらもない。
むしろ、悪い思い出が盛りだくさんだ。
鼻を劈く香水の匂いに、押し潰される勢いで何度も迫ってくる女の波。
あんな着飾った女だらけの魔の巣窟に、誰がわざわざ足を運ぶものか。
「夜会でレベッカをエスコートすれば、手っ取り早く周りに見せしめる事ができるでしょう」
「母さん、俺は婚約を承諾していない」
「ここまできてまだそんな事言うつもり?」
「ここまできてって、無理矢理つれてこられたんだ」
母は大きく溜め息をつく。
最近ちょっとご機嫌になったと思ったのだが、賢い息子は決して流されはしなかった。
息子の女嫌いの酷さも、その原因も重々承知している。
だが、今回の婚約ほどいい話など他に無い。
大国オードリアスの第一王女レベッカ。
身分も、彼女自身も問題ない。
彼女を逃して、一体誰を選ぶというのか。
「とにかく俺は出ない」
「だめよ。絶対出るの」
「断る」
零は突然腰かけていた窓辺から立ち上がり、早足で母の傍を通りすぎた。
母はまだ表情に不機嫌を残したまま、零の姿を目で追うように振り返る。
「零、どこ行くの?」
母の問いが終わる前に、零は部屋の扉を閉めた。
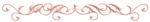
「夜会に出ろだなんて、外出禁止なのにおかしいと思わない?」
外出禁止、と言うわりにミシェルがいるのはいつもの書庫。
そしていつものようにソファの下の黒猫のマリンに話しかける。
いつもと違う事と言えば、ミシェルの右足だけが裸足な事くらい。
外出禁止の罰を下され、ミシェルの部屋の扉は開かなくなった。
押しても引いても蹴っても、びくともしない。
だが、そんな事ミシェルにとっては関係無い。
窓さえ開ければ、そこがたとえ四階でも、身軽なミシェルなら部屋の窓から窓を伝って移動する事ができる。
とても、王女のする事とは思えないが、その先入観が返ってバレずに済んだりする。
「でも今回の夜会まで放りだしたら、外出禁止じゃ済まされないと思うのよね。あの父親の事だから」
正義感溢れ、国の発展に尽力し、国民から多大な支持を得ている父、ランベール王。
そんな立派な父が、ミシェルは大嫌いだ。
ミシェルは大きく溜め息をつく。
さすがに今回は腹を括って、夜会に出るしかあるまい。
するとふと、その時本棚の向こう側からひょっこり顔を出した人物に気付く。
「あら・・・」
「どうも」
零は、ミシェルに一応軽く会釈した。
ミシェルの方は前と同じくソファの上に堂々と寝転がっていたが、前のように無表情でも睨むでもなく、少しだけ微笑んだ。
零は、懐から借りていた本を取り出す。
「これ、返しに来た」
「律義にどうも」
零は本棚の、一冊分空いているスペースに本を納めた。
そしてふと振り返れば、ミシェルはもうすでに読んでいる本に集中していた。
これまで会う女はみんな零に媚を売るようにしてくっ付いてきたのに、ミシェルだけは零に全く関心が無いようだった。
零は少し気まずそうにしたが、小さく決心したのか、赤いソファの上のミシェルに歩み寄った。
歩み寄ったまではよかったものの、ミシェルは気付いていないのかあえてなのか、零の方を見向きもしない。
やっぱりこのまま帰ろうか、と踵を返しかけたところで零はふと、ミシェルの読んでいる本に気付く。
「それって・・・魔法錬成呪文集?」
「あら、知ってるの?」
「あのオードリアス五十三代国王が書いた、原本しか存在しないといわれる・・・」
「あら、詳しいのねえ」
ミシェルは意外だ、というふうに目を見開いて零を見据えた。
零は、とても価値ある本がすぐ目の前にある事に些か興奮していた。
あの魔法錬成呪文集が。
有名な本ではないが、零にとっては喉から手がでるほど読みたい本だった。
前に一度母に頼んで、零にしては珍しく権力を振りかざして探させた程の本だったのだが、結局手がかりさえも見つかりはしなかった。
まさかオードリアスに国営の図書館とは別に、書庫があったとは。
そして誰にも利用されることなく埃被って眠っているこの書庫が、書物の宝庫だったとは。
零は、驚き硬直しながらも内心の興奮がミシェルに伝わったのか、ミシェルは小さく苦笑した。
「貸しましょうか?」
「えっ」
「すごく読みたそう」
零は思わず自分の頬に手をあてた。
掌に伝わる自分の頬は、熱い。
興奮からか、よほど紅潮しているようだ。
零は恥ずかしさから、さらに顔を火照らせた。
「はい」
「・・・でも」
「ちゃんと返してくれるでしょう?」
「ああ、必ず」
零は差し出された本を、恐る恐る受け取った。
手にした本は予想以上に重く、ずっしりとその価値を感じた。
零は妙に緊張したまま、惚れ惚れとその本の表紙を見つめる。
よほど零が感動しているのが可笑しかったようで、ミシェルは零に聞こえないよう笑いを噛み殺していた。
だが、口に手を当てて小刻みに震えているのだから、零はすぐにそれに気付く。
「何笑ってんだよ」
「あら、ごめんなさい・・・でも、あなたみたいな若い男がこんなマイナーな本が好きだなんて、変わってる」
「それはお前もだろ」
「私は自覚してるもの、変わってるって」
自覚は、あるのだ。
若い年頃の娘が、舞踏会より本が好きだなんて。
興味があるのは色恋沙汰の噂より、古人が残した希有な知識。
こんなの、変わってるとしか言いようがない。
「読書が好きなのは、別に珍しい事じゃないだろ」
「あなただって、初めて私を見た時思ったんじゃない?なんでこんなところに若い女がいるんだ、って」
図星を突かれて零は一瞬黙り込む。
それでも、彼女の射抜くような瞳に負けじと口を開いた。
「でも、お前は別に変じゃない」
真顔で言った零のその言葉に、ミシェルは一瞬目を見開いた。
そして変な沈黙の間があった後、ミシェルは何故か可笑しそうに微笑んだ。
「そう言ってもらえると、嬉しいわ」
「・・・いや」
零は少し照れたのを、頭を掻く仕草をして誤魔化した。
ミシェルが、ソファに寝転がっていた体をゆっくりと起こした。
細身の体に白い肌、長いブロンドの髪――――今日は結んでいないのか。
何故かミシェルの姿から目が離せなくなった。
そのとき、ミシェルの足元を見て零はハッと何かを思い出した。
「そうだ、これも返さないと」
そう言って零が懐から取り出したのは、黒いパンプス。
ミシェルは思わず「まあ」と声をあげ、すくっと立ち上がって零に駆け寄った。
「拾っててくれたのね、ありがとう」
ミシェルは零からパンプスを受け取ろうと手を伸ばしたが、零は寸前でパンプスを引っ込めた。
零の行動に、不思議そうに目を見開いてミシェルは自分より背の高い零を見上げる。
零はミシェルと一瞬目を合わせた後、その場に片膝をついて屈んだ。
「右足、出して」
ミシェルはやっと零の行動に納得したようで、無言で素直に右足を差し出す。
零は、そっと優しく、添えるように黒いパンプスをミシェルの右足に履かせた。
ふと見上げれば、ミシェルが少し無邪気に微笑んでいる。
零にとってその無邪気な笑顔は予想外で、衝撃的で、しばし零は茫然としてミシェルを見上げていた。
「お伽話を思い出すわ」
「あー・・・」
そう言われるとなんだか急に恥ずかしくなって、零は慌てて立ち上がる。
何故か熱くなる自分の頬を、手をあてて必死に冷やす。
ミシェルはそんな零に、小首を傾げて微笑みかけた。
「また、いつでもここに来ればいいわ」
「え?」
「あなたさえよければ」
ミシェルの、爽やかな柔らかい微笑み。
それはいつも零の周りに集る、化粧と媚の塊の笑顔ではなく、ごく自然な笑顔。
微笑みなれていないのか、左の頬が少しだけひきつっているのが控え目で何故か愛らしい。
それを見つめていると、零の中で何かが膨らむ。
感じた事のない、知らない何か。
不快ではないが、感じると緊張して体が強張ってしまう。
鼓動が速く脈打つ。胸が高鳴る。
だが知識の豊富な零でも、それが何かはどうしてもわからなかった。
もしこの時、気が付いていれば
彼女が自分の婚約者の妹だと気が付いていれば
その「何か」を止めることができたのだろうか。
| 

