第二話 昼過ぎ起床のシンデレラ
「ミシェル!!あなた一体どういうつもり!!」
ミシェルが部屋に戻った途端に、部屋に響き渡る怒号。
あれからミシェルはついつい読書に夢中になってしまい、目が覚めるとすでに翌日の昼過ぎ。
気付かれないようにこっそり自分の部屋へと戻ったところまではよかったが、部屋の中で鬼の形相をしたレベッカが待っていた。
「私の婚約者がいらっしゃるから、絶対に挨拶の場には居るようにってあれほど言ったわよね?!」
レベッカの顔はこれ以上紅潮できないほど血が上っている。
だが怒りのレベッカを見るのは珍しい事でもないので、ミシェルは面倒な人に捕まったと溜め息をついた。
その溜め息を聞いたレベッカは、言うまでもなくさらに怒り狂う。
「一体、私がどれだけ恥をかいたとッ・・・」
「わかったわよ、謝るわ。悪気は無かったの」
「お黙り!!お父様に言って、部屋から出ることを一切禁じます!!」
それだけ吐き捨てて、レベッカはミシェルの部屋から荒々しく去って行った。
嵐が過ぎ去ったところで、ミシェルはソファに寝転がる。
すると今までどこに隠れていたのか、黒猫がとことことミシェルの元へやってきた。
「あら、マリン。ちゃっかり自分だけ隠れちゃって・・・この卑怯者」
マリンはニャアと鳴いた後、ゴロゴロと喉を鳴らす。
ミシェルはマリンの額を指で弾いた後、お望みどおりに優しく撫でてやった。
この猫はいつも香水の匂いを振りまくレベッカが嫌いで、逃げていたらしい。
姉レベッカの婚約者である昴の国の王子は、端正な容姿をお持ちなことで有名だ。
だが婚約者候補が数多くおり、おそらく幼い頃から女達の汚い部分を嫌というほど見てきたのだろう。
彼の末期症状の女嫌いも、酷く有名な話だった。
だから今回の婚約も、おそらくは政略なのだろう。
だがレベッカ自身は単純に昴の王子に本気で熱をあげているらしく、大人たちの事情などは関係ないようだ。
しかし大人たちの事情も、レベッカの恋慕も、ミシェルには全く関係ない。
嫁ぐならさっさと嫁いでくれた方が、静かになって楽だというのがミシェルの本音だった。
「ねえ、マリン。レベッカから部屋から出てはいけないって言われたわ」
マリンは撫でられて気持ちよさそうに目を細める。
ミシェルは微笑みながら、マリンを抱き上げた。
「おとなしく引き下がる第二王女様じゃないわよ」
ミシェルは悪戯に微笑んだ。
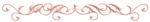
「で?結局第二王女様は見つかったのか」
「ええ、さっき見つかったらしいわ」
「ったく人騒がせな・・・」
零は大きく溜め息をつきながらも、それほど不快そうではない。
オードリアスに来てからずっと眉間に皺が寄っていた零が、今日は珍しくご機嫌である。
おそらくその原因は昨夜からずっと大事そうに抱えているあの本にあるのだろうと、母は推測する。
「なあに?その古い本」
「別に」
零は母までも警戒するように、本を大事そうに懐にしまい込む。
呆れたとばかりに母は溜め息をついて、首を横に振った。
すると、部屋の扉がノックされて母の侍女が顔を出す。
なにやら短く話し込んだ後、母はこちらを振り返った。
「ちょっと、ランベールのところに出てくるわね」
「ああ」
振り向きもせず、零は窓辺で庭園の景色を眺めながら言った。
そしてすぐに背後で扉が閉まる音が聞こえる。
今日は天気も良く、窓辺に腰かけていると爽やかな風が零の短い漆黒の髪を撫でていく。
一人は、非常に心地いい。
すると、突然どこからかガリガリガリという奇妙な音が聞こえてきた。
「・・・あ?」
平和な時間を邪魔する騒音に、零は思わず顔をしかめる。
音は、どうやら窓の外からするようだ。
零は音の根源を確かめようと、窓から顔を出した。
「・・・。」
そこにいたのは、黒猫だった。
零の部屋の窓のすぐそばの壁に、張り付いている。
どうやら音の正体は、爪を引っ掛けて壁伝いにどこからかやってきた黒猫だったらしい。
だが、ここは三階だ。
目の前の状況をよく呑みこめぬまま、零は無言で黒猫と見つめ合う。
すると、突然自分の顔に影がかかる。
何だ、とばかりに上を向いた瞬間、とてつもなく大きな物が零の頭上に降ってきた。
「げっ」
思い切りそれは零の顔面に衝突し、その重さと痛みに零はふらふらとソファに倒れ込んで悶絶した。
そしてふと、ソファから顔を見上げれば窓辺に何者かが立っている。
さっき降ってきたのは、人間だったのか。
「あーっ・・・やばかった」
予想外にも若い女だった。
そしてその質素な男のような格好と、美しいプラチナブロンドの髪に零は瞠目する。
まさか。
「お前っ・・・昨日の」
「げっ」
こちらを見上げる顔は、間違いなくミシェルという女だった。
ミシェルは思い切り顔をしかめ、慌ててあたふたと辺りを見回す。
くっそーまずいな、という呟きが彼女の方から聞こえた気がした。
「・・・お前、そこで何やってたんだ?」
「いや・・・」
「まさか、猫と同じで壁にはりついてたんじゃ」
「いや・・その・・・」
「正気か?」
ミシェルは些かばつの悪いような表情を見せた。
その場に気まずい沈黙が流れる。
その時、零が思い出したように口を開く。
「・・・そういえば、昨日の本だけど」
「ここで私に会った事、決して口外しないでね」
「え?」
「誰の目にも触れたらいけないの」
きょろきょろして辺りの様子を窺っている辺りが、何とも怪しい。
普通なら泥棒か何かかと思うのだが、これほど難しい本を愛読している者に悪人はいないと無理矢理信じることにする。
「・・・わかった」
すんなり了承した零に、ミシェルは一瞬目を見開く。
そしてまた、昨日のように柔らかく微笑んだ。
しかし、次の瞬間その微笑みが一瞬にして強張った。
突然、部屋の扉が開いたのだ。
「ねえ、零。これからレベッカと・・・零?」
一体、自分はどんな顔をしていたのだろうか。
部屋の入口に佇んでいた母が歩み寄り、心配そうに零の顔を覗き込んだ。
「どうしたの?顔が真っ青よ」
ハッとして、零は素早く辺りを見回す。
が、そこにミシェルの姿も黒猫の姿も無かった。
そういえば、あいつは魔法が使えたっけ。
部屋のどこにもいないことを確認すると、どっと安堵感が零の胸に押し寄せる。
が、それも次の瞬間再び青褪めることになった。
「あら?そこに何か・・・」
零は素早く母の視界を遮るように、目の前に立ちはだかった。
そして後ろ手で母に気付かれないよう、窓辺に落ちていた何かを魔法で自分の手元に手繰り寄せた。
「ちょっと、なーに?」
「いや、何でもない」
零はほっと一息ついて、後ろ手にその何かを持ったままソファに座りこんだ。
母も、怪訝そうに零の様子を見ながら向かい側のソファに腰を下ろす。
「ちょっと曇ってきたわね・・・雨でも降りそう」
母は立ちあがり、窓辺に歩み寄って窓を閉める。
零はその隙に、後ろから何かを母には見えないようこっそり取り出した。
黒い、パンプス?
ミシェルの履いていた物か。
辺りを確認したが、どうやら右足の方だけらしい。
慌てて行った為に落としてしまったのだろう。
どこかの童話のような、デジャヴ感があったがただの偶然だろう。
それにしても。
年頃の女が、まさか窓からやってくるなんて。
零は自分でも無意識のうちに、ふっと微笑んでしまった。
それに気付いて、慌てて笑みを消す。
母の方をちらりと見てみたが、母は雨が来るのを心配そうに窓の外を眺めているだけだった。
零はそっと黒いパンプスを母に見つからないよう、懐に隠すようにしまい込んだ。
| 

