第四話 月夜の下のバルコニーにて
扉を開けたとたん、耳に流れ込む会場の騒音、目の前に広がるのは煌びやかな紳士淑女。
天井から吊るされた豪華なシャンデリアが目障りなほどに美しい。
ミシェルはざっと会場を見渡して、誰の目にも触れぬように会場の隅の方へと歩いていく。
だが、結いあげまとめられたミシェルの綺麗なブロンドの髪は目立つのか、すれ違うほとんどの人々の目がミシェルへ向けられる。
ミシェルはそれを鬱陶しげにかわしながら、幾重にもなっているカーテンをくぐり抜けて人気の無いバルコニーへと足を進めた。
「はあ・・・」
溜め息が、突然強まった夜風にかき消される。
極力目立たないよう華美でない黒一色のドレスを選んだのだが、そのドレスの色が自身の髪の色を引き立てて逆に目立っている事に後で気づいた。
振り返ってカーテンを少し開けば、会場の中央にレベッカがいるのがすぐにわかった。
豪勢で華美なドレスはフリルを惜しみなくあしらい、鮮やかなピンクがこの会場で一番目立っていた。
呆れ半分尊敬半分で、レベッカをしばらく目で追っていると、レベッカは自身の周りに群がる貴族達を上手く相手しながらきょろきょろと周りを見渡している。
そういえば、肝心の婚約者らしき人物がレベッカの周りにいない。
「婚約者を見せびらかすための夜会でしょうに・・・」
何故、婚約者の姿が無いのかはわからない。
だが、それはレベッカも同じのようで、いつも自信に満ち溢れているレベッカには珍しく少々不安の色が表情に滲み出ている。
でもおそらく会場に入ったときには婚約者にエスコートされているはずなので、最初からいなかったわけではないだろう。
エスコートの相手を放り出すなんて、無責任な。
昴の王子は、大丈夫なのか?
でもミシェルにとっては都合がよい。
このまま婚約者が現れずに、自分の出番も無くなればいいのだが。
なんて、勝手にもミシェルは願っていた。
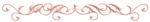
「ここにいた!!」
目立たぬよう会場の隅の方でじっとしていた零だったが、とうとう母に見つかってしまった。
いつも着物の母だが、今日の夜会では艶やかなモーヴ色のドレスを身にまとっていた。
世界中の誰もが口をそろえて、母は美しいと言う。
それは事実だとは思うのだが、今母が零に向けた顔はしかめっ面をしていて到底美しいとは言えなかった。
「今すぐレベッカのところに戻りなさい!」
「断る」
せっかく一瞬の隙をついて抜け出してきたんだ。
誰が自ら魔の巣窟へと戻るかってんだ。
エスコートしている最中も嗅覚を狂わせる程の香水の香りが零を襲う。
さすがに呼吸をしないわけにもいかないので、我慢の限界を超えた零は途中で逃げてきたのだ。
「あなたって人は・・・」
母はわざとらしく大きく溜め息をつく。
零は、決して母が嫌いなわけではない。
一国の女王として荒れていた国の治安を立て直し、民からも慕われて、多忙な中で幼い零にも構ってくれていた。
理解力もあり信頼もでき、そして未だ口でも力でも敵わない母。
良好な親子関係の間で唯一、互いに頑として譲らないのが結婚の話だ。
昔から母が片っ端から連れてくる婚約者候補を、これまた零は片っ端から拒絶し泣かせてきた。
それでも互いに譲らなかったがこの間持ってきた母の婚約話は、なんと相手はあの大国オードリアス第一王女レベッカ。
国の友好関係にも響きそうで、少し零が躊躇ったその隙をついて母は無理矢理零を国から連れ出した。
零は、初めからきっぱり断ればよかったとそれはもう凄まじい勢いで後悔していた。
「俺は、今回の婚約を承諾していない」
「まだそんな事言うの?今回の話を逃したら、あなたはいつまで経っても結婚しないのなんて目に見えてるんだから」
「絶対に、嫌だ」
「零!」
零は、隙を見て背後で風に揺れていたカーテンの後ろに素早く逃げる。
後ろで母が不機嫌な声で自分の名を呼んでいるのが聞こえる。
追いかけてくるだろうか。
零はまとわりつくカーテンをかいくぐって、足音を立てず気配を消して走る。
すると、突然幾重にもなっていたカーテンの波が終わって、開けた空間に出た。
「バルコニーか・・・」
目の前に広がる美しい夜空。
どこの国でも、夜空の色は同じなのか。
優しく髪を撫でる夜風が、気持ちいい。
なにより、厚いカーテンの層で会場の喧騒がほとんど聞こえない。
静かで、気持ちのよい場所を見つけた。
「誰?」
何者かの声にハッとして、後ろを振り返る。
全く気配に気づかなかった零は、警戒心を露わにして数歩後ろへ下がる。
そこには、黒いドレスを身にまとったプラチナブロンドの女が立っていた。
綺麗に結いあげられた髪に、薄いながらも施された化粧はいつもと違って、一瞬誰かわからなかった。
「お前・・・ミシェルか」
「あら」
ミシェルの方も、零が誰かわかっていなかったようで、険しかった面持ちを少しだけ和らげた。
零は、改めてミシェルの立ち姿を眺めてみた。
プラチナブロンドの髪以外、いつもの姿と違いすぎる。
普段は化粧もせずに男のような格好をしているのに、今日はどこからどうみても女だ。
「・・・お前もそういう服着るんだな」
「どういう意味よ?」
「いつも男みたいなのに」
言ってから失礼だったかと気付いたが、意外にもミシェルは微笑んでいた。
月夜の下で黒いドレスを纏って微笑むミシェルは、えらく艶やかだ。
「あなたもえらく着飾ってるじゃない。意外にも、結構お偉い人なのね?」
「意外にもって、なんだよ」
「見た感じだいぶ若いし、まだ何も知らない尻の青いヒヨコちゃんかと思ってた」
「酷いな…」
「青二才ってやつ?」
零も、思わず笑う。
自分に全く媚びてこないのは自分の正体を知らないからなのかもしれないが、それでも素の自分で話し合えるのは心地よかった。
このまま、ミシェルには自分の正体を知らないでいてほしい。
心からそう願った。
「でもミシェルだって・・・いつもはあんな身なりだから、よくて使用人かと思ってた」
「そんなにボロい服着てたかしら、私」
「ボロいっていうか・・・質素?」
「だって派手な物って、動きにくいじゃない」
「年頃の娘が動きやすさ重視かよ」
「周りの目をかいくぐって書庫に行くには、相当な運動能力と技術が必要なの」
「・・・お前ホントに何者だよ」
ミシェルの話からして、堂々と人前に出られる立場じゃない事は明らかだ。
でも、ちゃんと夜会に出席しているからには招待される身分ではあるのだろう。
それともこの夜会にも無断で隠れて出席しているのだろうか。
だいたい、人気のないバルコニーなんかにいる時点でそれは有り得る。
「零!!」
大きな声に後ろを振り向くと、不機嫌最高潮の母が腰に両手をあてて立っていた。
零と同じ色の髪が月明かりを反射させる。
相変わらずその姿は、美しいのにもったいない。
母はしかめっ面のまま零の方にずかずかと歩み寄ってきたが、ふと零の背後にいる人物に気付いたようで目線がそちらへ移る。
母は顔をきょとんとさせたが、すぐににっこりとほほ笑んだ。
「あら・・・もしかして、ミシェル?」
母の言葉に零は目を見開き、ミシェルの方をみやる。
ミシェルは、微笑んで軽く会釈をした。
「まあまあ、ミシェルじゃないの!」
母は嬉しそうにミシェルに駆け寄って抱きしめた。
少し苦しそうなミシェルと目が合う。
何故、母は彼女を知っているのだろうか。
零には全くわからなかった。
「紹介するわ、こちら息子の零よ」
「息子・・・って事は、王子?」
思わぬところで素性が知れてしまい、零はばつの悪そうな表情をしてミシェルから目をそらした。
ミシェルは心底驚いているようで、瞳を見開いて驚嘆の息を漏らしていた。
昴の国の王子だと知って、媚びない者などいない。
それが女だと尚更で、せっかく自分の正体を知らなかった貴重な存在を失い、零は心から落胆した。
そんな心情も露知らず、母は零の背中を勢いよく叩く。
「零、 知ってると思うけどこちらはミシェルよ」
「あなたが姉の婚約者だったのね」
・・・姉?
きょとんとする零に、母は驚いたように首を傾げた。
「知らなかったの?零、こちらはレベッカの妹の、オードリアス国第二王女のミシェルよ」
「どうも」
ミシェルは胸の下で腕を組んで、悪戯っぽく微笑む。
零は瞠目したまま、言葉も出ない。
オードリアス国第二王女?
化粧もせずに男みたいな格好をしてソファに寝転がっているこの女が?
窓から壁伝いに部屋に飛び込んできたありえない行動をするこの女が?
嘘だ、そんなわけないだろう。
否定を待ってみたが、それでも母もミシェルも微笑んだまま。
「・・・冗談、じゃないのか」
「失礼ね」
少し不機嫌を含みながらも微笑むミシェルの前に、零はしばらく開いた口が塞がらなかった。
| 

