第一話 Second Princess
――――――――帰りたい。
海を渡り、異国の地を踏んで二日目の朝。
零は、目の前の湯気立つ甘いお茶と桃色と白色の甘い砂糖菓子を見て無性にそう思った。
ホームシックというわけではない。
とりあえず、今この場所から逃げることができればどこへだっていい。
男はそう思いながら無言で砂糖菓子を睨みつけていた。
「あの・・・お口に合わなかったようで・・・」
ふと、砂糖菓子から目をあげると向かい側に座る女がこちらの機嫌を上目づかいで伺っていた。
この紅茶の湯気のように甘い匂いを振り撒いて、この砂糖菓子のように派手な色使いの服で自分を着飾っている。
「零」
無言で女を見据える零を、隣に座る母が小突く。
零は母に聞こえないように舌打ちしたつもりだったが、やはり聞こえていたようで周りに見えないよう太股を強くつねられた。
痛さに一瞬顔をしかめ、零は不承不承ながらも砂糖菓子に手を伸ばす。
口の中にそれを放り込めば、口の中に広がるのは甘味料の甘さだけ。
甘ったるい。
洋菓子は、どうしてこうも甘いんだ。
甘ければいいってもんじゃないだろう。
口直しに紅茶を流し込むが、あまりの甘さに思わずむせてしまった。
「あら、どうしたの」
心配そうにこちらを覗き込む母の視線を交わして、零はもう絶対に洋菓子なんか食うもんかと決めこんだ。
だいたい、茶まで甘いなんてどうかしてる。
零は不機嫌を隠すことなく表情に露わにして、ふいっとそっぽをむいて窓の外の景色を見やる。
目の前に座る女は、零の機嫌を損ねてしまった事が相当ショックだったらしく、目に見えて落ち込んでいた。
「零!どうしてあなたって人は・・・」
母の小言にも全く耳を貸さず、零は窓の外から目線を動かさない。
隣で母のため息が聞こえる。
それは零が聞いた本日何度めの溜息か。
それはおそらく聡明で明哲な母自身も、優秀な母の侍女でさえもわからないだろう。
ここは大国オードリアス。
広大な土地に豊かな資源、ここに来る時に見た賑やかな市井がとても印象的だった。
世界的に衰退の一歩を辿る魔法に関しても、この国には未だ優秀な魔術師がたくさんいる。
オードリアスは今世界で最も発展している国といっても過言では無い。
そして今、零の目の前に座っているこの甘ったるい女は、この国の第一王女レベッカである。
そして零の婚約者。
可憐な所作と愛らしい笑顔が庶民に人気だという。
零はその売り文句を心の中で嘲笑った。
「それにしても賑やかな街ね。あとで買い物に出掛けたいわ」
「それでしたらこちらからも侍女と護衛の者を手配しますわ」
「ああ、侍女は結構よ。護衛の方はお願いするわ」
「かしこまりました」
にっこりと微笑むレベッカを見て、なるほどこれが噂の愛らしい笑顔か、と零は思う。
だが零の捉え方は庶民とは違ったらしく、零はレベッカの微笑みを見て眉間に皺を寄せた。
すると、その時零の背後の扉が開く。
「遅くなってすまないね、零君に歌蓮」
母である歌蓮はにっこりと微笑み返したが、零といえば無愛想な表情を少しひきつらせただけだった。
部屋に入ってきた人物は、赤みの強い金髪が特徴的な四十代半ばの男性。
その髪の色は零の目の前にいる婚約者と非常によく似ている。
言わずもがな、目の前にいるこの男こそオードリアス国王、ランベール・オードリアスである。
ランベールはよっこらせ、と歌蓮の目の前、レベッカの隣に腰を下ろした。
そして顔を上げた時にランベールは零と目が合う。
なぜ、斜め向かいの零と最初に目があったのか、零は疑問に思ったが決して表情には表わさなかった。
すぐに目線は逸らされ、ランベールは歌蓮に穏やかに微笑む。
「二人とも遠路遥々、我が国オードリアスへようこそ。長旅で疲れているだろう?」
「いいえ、昨日一日休んだから大丈夫よ。後で城下を散策でもしようってレベッカと話していたの」
「おお、私の知らないところで親睦が深まっているようで何よりだ。ところで・・・」
ランベールは、何やら意味ありげにレベッカの方を見やる。
レベッカは父であるランベールと目を合わせると、申し訳なさそうに首を横に振った。
ランベールはそれを見て小さく溜め息をついて、頭を掻きながら歌蓮達に向き直った。
「申し訳ない、挨拶をさせねばと呼んでおいたのだが・・・」
「誰を?」
ほとんど初めて零が口を利いたことに、レベッカは安心したように少し顔を綻ばせた。
しかし、すぐに彼女はその安心した表情を再び引き攣らせた。
「私の、妹なんですが・・・」
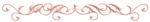
「ぅぶえっくじゅ!」
年頃の娘のものとは思えない盛大なくしゃみが、広い書庫に響き渡る。
幸い、読みかけの本は鼻がひくついた時点で避難させておいたので無事だ。
そして女は鼻をすすりながら、再び本を開く。
ここは、オードリアスの王宮の一角にある書庫。
この書庫には膨大な量の書物が納められているのだが、オードリアスの王宮には隣接している巨大な図書館がある。
ではなぜ王宮に書庫なんかがあるのかといえば、風変りな学者さえも見ないような珍しかったりつまらなかったりする本が納められているのだ。
広い書庫内には天井にまで届いている本棚がずらりと並び、そして重力に逆らってどうやって並んでいるのか天井まで本棚と化している。
そして何故かその本棚は不規則に置かれている為に、書庫は迷宮化していた。
その迷宮を迷う事なく進むことができれば、一番奥に開けた空間がある。
その空間の真ん中にポツンとおかれた赤いソファ。
そこに女は寝転がっていた。
白く長い足を放り出し、仰向けになって本を読んでいる女の名前はミシェル。
腰まで届く長いプラチナブロンドの美しい髪は、無造作に高く結いあげられている。
皺くちゃの白いシャツに黒いタイトなパンツという格好は豊満な胸さえ無ければ男のようだ。
ミシェルは大きく欠伸をして、そのときふと何かを思い出した。
「ねえ、マリン」
ミシェルは、ソファの下で眠る黒猫に声をかける。
「今日、何か予定があった気がするんだけど・・・」
記憶の片隅にある何かを、必死に思い出そうとするがもがけばもがくほど何かは沈んで見えなくなる。
それが大事なことなのかそうでもないのかさえ、思い出せない。
「・・・ま、いっか」
ソファの下からのぞく黒い尻尾を撫でて、ミシェルは再び本に目を戻した。
するとその時、書庫の重い扉がゆっくりと開く音が聞こえた。
この書庫は場所が場所なだけに存在さえあまり知られておらず、滅多に誰も来ることは無い。
ミシェルは顔を上げ、訝しげに音のする方へ目をやる。
程なくして扉が閉まる音がしたが、果たして人物が出て行ったのか書庫に残ったのかはわからない。
足音は聞こえない。やはり去ったのだろうか。
しかし、ミシェルは扉の方から目を離さなかった。
この開けた空間へと続く通路は一つしかない。
本棚に囲まれたこの空間の中の唯一の隙間を、ミシェルは瞬きひとつせずじっと見つめる。
足音は、やはり無い。
だが、微かな気配を感じていた。
やがて、その人物は現れた。
黒髪の東洋の顔立ちをした男が、ミシェルを見て瞠目している。
こんな辺鄙な場所で、若い女が寛いでいるからだろう。
ミシェルは、その男を全く知らなかった。
とすれば、男はこの書庫に来たのは初めてのはずだ。
初めてにして迷宮を抜けてこの空間へ辿り着けたのは、ただの偶然なのだろうか。
「・・・お前は、誰だ?」
男の年齢は自分とそう変わらないように見える。
ミシェルは十八、おそらく男もそれくらい。
男の身なりは随分といい為、使用人というわけではないだろうが、その言葉遣いにミシェルは少々気分を害した。
「名を訊くなら、自ら名乗れ」
不機嫌そうに低音でそう告げれば、男の方も不機嫌そうに顔を引き攣らせた。
だが、尤もだと思ったのか、男は渋々といった様子で口を開いた。
「・・・零だ」
聞き慣れない発音の名前からして、やはり東洋の人物なのだろう。
そこでミシェルはふと、何かに思い当った。
そういえば、今日はレベッカの婚約者がやってくると言っていなかったか。
しかもその婚約者というのは昴の国の王子ではなかったか。
・・・いや。
ミシェルは徐々に繋がっていく思考を、自ら妨げた。
王子様がこんな場所に来るはずないだろう。
埃被った古い書物だらけのこんな場所に。
「お前の名は?」
ソファに仰向けに寝転がっているその体勢を崩すつもりは無いらしい女を見て、零が不機嫌を示したのは明らかだった。
だが、ミシェルはそんなのを気にするような素振りも見せず、しまいには頬杖をついてこちらを見上げた。
「ミシェル」
端的に、ミシェルはそれだけを述べた。
向こうも身分を明かさなかったので、こちらも身分を明かさない。
男と同じように、名前だけを告げる。
男はしばらくミシェルを見つめ、やがて目線を周りの本に移した。
天井さえも本棚になっているこの空間で、本が見当たらないのは床ぐらいしかない。
読書好きのミシェルにとっては堪らない空間だが、そうでない者にとっては酷く退屈でしかないだろう。
だが、男は決して退屈そうには見えなかった。
「外の図書館とは別なのか?」
「ええ。一般の人に貸出はできないわ」
「でも、貴重な本なら図書館の貸し出し禁止書物にできるはずだ」
「そこにあるものよりもずっと貴重で、ずっとつまらないのよ、ここの本は」
ミシェルは面倒臭そうにそう言った後、男から目線を本に戻した。
男は近くにあった本棚の一つに近寄って、納められている本の一つを手に取った。
互いに本を読むことに集中し始めた為、書庫には沈黙が訪れる。
時たまページを捲る音が聞こえ、ミシェルはふと本から目をあげる。
男が夢中になって本を読んでいるのを見て、不思議そうにそれを見つめる。
「あなた、何しに来たの」
すると男は、我に返ったかのようにハッと顔をあげて、こちらに向き直った。
だが、しっかりと本は読んだページまで開かれたままでしっかりと胸に抱えられている。
「第二王女を探しに来た」
「・・・。」
無表情だったミシェルの顔に、ふっと暗雲が立ち込めたように見えた。
「レベッカの妹だ」
「知ってるわよ・・・名前も知らないわけ?」
「ああ・・・そういえば、聞いてないな」
「名前も知らずに探すなんて、どうかしてるんじゃない」
ミシェルは溜め息をついて、ソファの上で寝がえりを打つ。
向こうを向いてしまったミシェルを見て、零は困ったように頭を掻く。
「知らないのか?」
「・・・大体、年頃のお姫様がこんなところに来るとでも思ってるの?」
「・・・。」
それもそうだな、と納得したように零は黙り込む。
そうしてしばらくの沈黙があり、零はミシェルの背を見ていたが、やがてミシェルに背を向けた。
しかし、背を向けたところではたと立ち止まる。
「・・・あのさ」
零の問いに、ミシェルは無言ながらも顔をこちらに向けた。
「この本・・・貸出禁止?」
この本、と言われて目をやれば、自分が読んだページを指を栞代わりにはさんで大事そうに抱えている古い本があった。
それは紛れもなくさっき零が適当に手に取ったこの書庫の本で、ミシェルはまさかこの男がそんなにもここの本を気に入るとは思っていなかった。
年頃のくせにこんな気難しい本が好きな奴、自分以外にもいるもんだな。
しかし、それとこれとは別である。
さっきも言った通り、この書庫の本は図書館の本とは違って貸出禁止だ。
どれも世界に一つしかないような貴重な書物なのだ。
万が一戻ってこなかった時の保証がどこにもない、ましてや他国の者なんかに貸すわけにはいかない。
「ええ、禁止よ」
「・・・でも一般の人はだろ?」
「あなただって一般じゃない」
その言葉に、零は口を噤む。
そして零は名残惜しそうに抱える本を見つめ、まるで恋人と別れるかのように心残りありまくりの表情で本を棚に戻した。
その時、何気なく零は小さな声で呟いた。
「・・・一応、王子なんだけどな」
しかし、彼の呟きは小さすぎてミシェルには届かなかった。
彼にとってもただの独り言に過ぎなかったので、その呟きは空に消える。
零は棚に戻した後も、やっぱり未練があるようでしばらくその本を見つめていた。
が、やがて一息をついてミシェルの方に視線を向けた。
「・・・邪魔したな」
零はそれだけ言って、ミシェルに背を向け歩き出す。
零が本棚の向こうに消える瞬間、ミシェルは無意識に彼を呼びとめていた。
「ねえ」
零の方も、その声に立ちどまる。
本棚の向こうから顔だけこちらに覗かせれば、自分と同じように無表情の顔がこちらを向いていた。
「・・・絶対にここに返すって誓う?」
最初は何の事を言っているのかわからなかったが、すぐに零は思い至った。
ミシェルは、射抜くような鋭い瞳で零の答えを待っていた。
「・・・トート神に誓って」
知恵の神であり書記の守護者である神の名を出した零に、思わずミシェルは微笑んでいた。
それを見て、零は思わず瞠目していた。
・・・笑うのか。
最初見た時から無愛想で心底憎たらしい女だとは思っていたが、意外に可愛らしく笑う。
その愛らしさは自身の婚約者のものとは明らかに違い、甘い砂糖菓子ではなく、瑞々しい果物のような爽やかさだった。
「いいわ、持って行って」
「・・・ありがとう」
零は本棚のところまで戻ろうとしたが、コトコト、と聞こえた何かの音に零は足をとめた。
すると零が先ほど棚に戻した本がふわり、と棚から飛び出して宙に浮いた。
零が目をぱちくりさせていると、本はそのままふわふわと浮遊したまま生きているかのように零の胸元へ飛び込んできた。
・・・この女の魔法か。
指さえ動かさずに浮遊魔法を操るなんて、この女はどうやら見かけによらないらしい。
このミシェルという女は、零が会った女の中で一番無愛想で一番礼儀を知らず一番質素な格好で、そして一番興味深い。
「・・・また来る」
「第二王女様によろしくね」
零が目を見開いたところを見ると、本に夢中で人探しの最中だという事を忘れていたらしい。
思わずミシェルが笑えば、零も僅かながらに微笑み返してきた。
そして零は大事そうに本を抱えたまま、本棚の向こう側へと姿を消した。
やがて、書庫の扉が閉まる音が聞こえた。
オードリアス国第二王女ミシェルは、仰向けに寝転がったまま本の次ページを捲った。
| 

