第五話 時と場合によっては責任転嫁は正論である。
「おーい、鈴代ー。おーい」
ハッと気付くと超至近距離に睦月の顔があって、鈴代は驚いて飛び上がる。
その拍子に机の上のスナック菓子が数個床に転げ落ちる。
睦月は不思議そうに鈴代の顔を覗きこもうとするので鈴代は慌てて顔をそむけた。
「何だよ!ちけーよ!」
「何回呼んでも返事しねーからだろ」
むむむ、と鈴代は不機嫌に唇を尖らせる。
何も知らない睦月の顔を見ると、胸の中で昨日の事がもやもやしてくる。
そして鈴代はちら、と教室の端にいる白鳥美海に目をやった。
今日は日直なのか、一人で丁寧に黒板の字を消していた。
今日一日観察してみて、白鳥美海の様子は特にいつもと変わりなかった。
果たして、あのあとどうなったのか。
鈴代は気になってしかたなかった。
あの一番大事な場面を、鈴代は逃してしまったのだ。
「くそっ、どれもこれもお前のせいだ!」
「そういうの責任転嫁っていうんだよ」
「うるせー!丞のくせに!」
あの時、本棚の物影から鈴代が白鳥美海と霜月の様子をこっそり盗み見していたとき。
いや、別に悪気があってやったわけじゃない。
そう、断じてそういうわけではない。
ただ、ばったり偶然はちあわせてしまっただけなのだ。
それをコイツが・・・
「なーにしてんのかなー」
「うっわあ!」
「人の告白を覗き見?趣味悪いね〜」
「なッ、違ッ、私は丞を…」
「ハイハイ、とりあえず静かに図書室を出ましょうね〜」
そして丞に強制連行され、結局一番重要な部分だけを見逃してしまったのだ。
そう、どれもこれも丞のせい!
丞のアホが最悪のタイミングで・・・
「すげー目つき悪いんですけど」
「うわーホントだよ。女子として終わってるよ」
「うっせーな!だーっとけ!お前のせいで昨日はなあ!!」
「だーから、そーゆーのを責任転嫁って」
「え、昨日がどしたの?」
きょとんとこちらを見つめる睦月に、鈴代は思わずハッとなる。
丞の方を見てみるが、違う方を見つめて知らんぷりを決め込んでいる。
首を傾げて答えを待つ睦月に、鈴代は微笑み返すが頬が完璧にひきつっていた。
言うべきなのか。
言わざるべきか。
「あっ、てゆーかさあ!丞!」
鈴代が迷っていると、突然思い出したように睦月ががばっと顔をあげる。
「勉強教えて!!」
「・・・・突然どうしたの」
「1位になる!!」
「・・・・それはまた」
「ね、丞なんとかいってやってよ。昨日からこんなんなんだよ、睦月」
鈴代が大きくため息をつくが、睦月は目を爛々と輝かせて丞を見つめている。
丞は首を傾げて、廊下の方をくいっと顎で示した。
「学年3位の俺よりも、学年2位のお兄ちゃんの方がいいんじゃない」
「・・・。」
睦月は眉間に皺を寄せて、睨むようにふくれっ面になる。
果たして、丞はわかってて口にしたのか。
丞は無言で唇の端に少し笑みをのせて、睨んで来る睦月を見てどこか楽しんでいるようにも見える。
頭脳派不良の考えている事はさっぱりわからない。
「じゃ、今日の放課後ぐらいに相模家庭教師になりますか」
「いぇ〜相模先生サイコー!!」
「てことで鈴、俺今日睦月ん家寄るから」
「ん?え、ああ・・・おぅ」
そこで鈴代は、ふと思い出す。
そういえば昨日は丞に、睦月の事が好きだと打ち明けようと思って図書室へ行ったんだった。
すっかり忘れていた。
きっと丞は察してるけど、でもやっぱり自分の口から言わなければいけないと思う。
とは思いつつも、一晩たって冷静になるとやはり言いづらくなってしまった。
今日は帰りに丞の家寄れないし。
丞の方を見上げると、さっきからずっと鈴代の方を見ていたかのように目が合う。
丞の目はいつも通り優しく見守っているようで、でも。
でも、少しだけ冷たいような。
寂しいような感じがした。
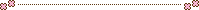
「・・・ただいま・・・・あれ」
壁の向こうで玄関のドアが開いた音がして程なく、リビングに霜月が入って来た。
そしてテーブルで睦月の向かい側に座っている人物を目にとめる。
「おー、おかえり」
「ども」
丞は顔をあげて、軽く会釈する。
霜月は物珍しそうに丞と睦月を交互に見て、ふらっとこちらに歩み寄って来た。
丞はそれを気にすることなく手元に目線を戻したが、睦月の方は近づいてきた霜月から睨むように目を離さなかった。
「へー・・・勉強?最近どうしたの」
「おめーには関係ねーよっ。おら、どっか行け」
「そーいうところは不良なんだね・・・」
元からそこまで睦月に興味が無かったのか、霜月は睦月を一瞥しただけであっさりとリビングに隣接する階段へと離れた。
そこでふと丞が手を止めて、階段の方へ顔を向ける。
「霜月」
ぴたりと階段を上る霜月の足音がとまる。
リビングからはすでに霜月の膝下のみしか見えないが、霜月がゆっくりと階段を降りてきた。
笑いもしないが睨みもしない丞の無表情に、霜月は不思議そうに首を傾げる。
「・・・・くん、つけた方がいい?」
「や、霜月でいいすけど。睦月と仲いいし、名字もあれでしょ」
「そうなんだよね」
「・・・で、それだけ?」
丞は一度、重たく瞬きをした。
「彼女、いる?」
丞のその質問に、霜月はしばらくそのまま丞の方を見つめ返していた。
霜月は少し目を細めて、丞の方を窺っている。
丞の質問から何かを感じ取ったのだろうか。
だが、その何かは結局わからなかったようで、霜月はふっと息をついた。
「いないけど」
「へえ、モテるのにね」
「相模には敵わないと思うけど」
そう言って霜月は静かに階段をのぼっていった。
しばらく霜月がいなくなった階段の方を丞はじっと見つめる。
その丞の横顔に、ふっと笑みが横切ったのを、睦月は無言で見つめていた。
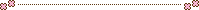
「・・・入るときはノックくらいしてよ」
睦月はわざと大きな音をたてて霜月の部屋の扉を開けた。
こちらに振り向いた霜月は、珍しい来客に少し驚いているようだった。
中学校に入るまでは一つの部屋で一緒に過ごしていたのだが、部屋が別々になってからは全くと言っていいほど霜月の部屋には入った事がなかった。
自分の部屋とは違って物が少なく質素で、綺麗に整えられていた。
見たところ漫画もゲームも無く、学年2位はそんな事をする暇もないのだろうかと思った。
「何だよ、見られて困るもんとかあんのかよ」
「別に無いけど。何の用?」
「ノート貸せ」
「・・・何の」
「現国の」
小さな声でそう言った睦月の顔を、霜月はかなり怪訝そうに見つめている。
警戒しながらも霜月は無言で机の上の本立ての中から一冊の青いノートをとりだして、睦月に差し出した。
「・・・落書きとかしないでね」
「しねーよ!」
霜月はまだ、あの睦月が単純に勉強の為だけにノートを借りるとは思っていないらしく、睦月がおとなしく部屋を出ていくのか最後までこちらを見ているつもりのようだった。
睦月は刺すような霜月の視線に居心地の悪さを感じながらも、思い切ってドアノブにかけた手を離して、霜月の方に向き直った。
対峙すれば、霜月の鋭い眼光に射すくめられた。
「お前さ、彼女いねーの?」
「何、それを聞く為にわざわざノートなんか借りにきたわけ?」
「ちげーよ!ノートのついでだよ!」
しかし、睦月の言う事など鼻っから信用していないようで、霜月は呆れた目で睦月を見ている。
「相模にも言ったけど、いないって言ったじゃん」
「でもお前モテんじゃん。なんでつくらねーの?」
「睦月だってモテるのに彼女いないじゃん」
「俺はそれなりの理由があんだよ!」
「理由って?」
「誰がお前なんかに言うかよ!」
そこで睦月ははっとする。
気付けば、またいつものように話の主導権を霜月に握られてしまっていた。
くそっと呟いて、再び霜月の瞳を見やる。
そこには自分と違って随分大人びている同じ顔があった。
「お前さ、好きな人とかいんだろ」
「何、急に」
「だから彼女つくらねーんだろ」
「・・・睦月、そーなわけ?」
「俺の話は今してねぇんだよ!」
何故かむきになる睦月に、霜月は相手の腹を探るように目を細めてこちらを射すくめる。
双子の弟のはずなのに、自分と同じ顔のはずなのに、何故かその目が少し怖かった。
「別に、いないけど」
「嘘つけよ」
「嘘なんかついてどーすんの」
「恥ずかしがってんだろ!」
「・・・好きな人がいるって、根拠でもあるわけ?」
くっ、と言葉につまる睦月を見て、霜月はやはり呆れたようだ。
小さくため息をつくと、霜月は睦月から目をそらして向こうを向いてしまった。
どうやら睦月が部屋に来るまで本を読んでいたらしく、ページを捲る音が聞こえる。
「・・・白鳥美海か?」
「何が」
「お前の好きな人」
霜月の全ての動きが一瞬、止まったように思えた。
霜月は、再びゆっくりとこちらに向き直る。
その目はやはり、鋭かった。
「・・・・いや?」
霜月は重々しく口を開く。
睦月は、霜月の無表情に負けじと唇を真一文字に結んで対峙する。
「まあ・・・向こうは好きみたいだけど」
「は?どーゆー意味・・・」
「ふった」
「へ?」
思わず、間抜けな返事をしたことにも睦月は気付いていなかった。
睦月はわけのわからないまま霜月の方を見つめるが、霜月は、相変わらず無表情だった。
「告白されたけど、ふった」
睦月は頭の中が真っ白になる。
さっきまで固く結ばれていた唇はいまや全開で、ぽかーんとしたいかにもな間抜け面を晒している。
霜月はそんな睦月を見てどう思ったのか、ため息をついてはいるが無表情は崩さない。
「何なの?」
棘のある苛立った口調で霜月が睦月に問う。
「睦月だって告白されてふるなんて日常茶飯事にあるだろ」
霜月は早く出てけ、と言いたげな目で睦月を見やり、再びこちらに背を向けて本を読み始めた。
睦月はしばらく、双子の弟の背中をじっと見つめていた。
自分とほとんど同じ身長で、体つきもほとんど同じ。
顔だって、髪の色以外全く同じ。
なのに、どうしてこうも中身が違うのだろう。
どうして俺の方が、こうも欠陥品なのだろう。
睦月は、今に始まった事ではない劣等感が、胸の中で膨らんでいく気がした。
殺意ではない。
だが、似たような濁った鈍色が腹の中で渦巻いていた。
| 

