第三章 任務
「はじめまして、アリアくん」
頭上の豪勢なシャンデリアは、控え目に、優雅に部屋を照らす。
豪華な部屋の装飾や家具に気を取られていたアリアは、聞こえた自分の名前にふとそちらを向く。
目の前には、見知らぬ男性が一人。
三十代後半か、四十代前半くらいの体つきのいい男性は、アリアや星羅がいるところより一段程高い
ところにいるので、こちらを見下すように椅子に腰掛けている。
部屋の豪華な内装にしては少し地味に見えるアンティーク調の椅子は、玉座でこそないがおそらくそ
こに腰掛けているその男性こそ、この国の国王。
「バロック・ギルデ・バルトだ。よろしく」
腰掛けたまま差し出された手に、アリアはふと気付いて椅子の前まで歩み寄る。
その手をとったとき、至近距離でバロックは何故かアリアの瞳を驚くほどじっくりと見つめている。
アリアの左右で色彩の違う瞳が、それほど珍しいのだろうか。
アリアは儀式的にさっさと握手を終わらせ、そそくさと先程いた位置まで戻った。
その時も背中に感じる突き刺さるほどの鋭い視線が、どんな意味を含んでいるのかまでアリアにはわ
からなかった。
「知っての通り、我々は十七年前に失った世界の平和を取り戻す為に在る」
十七年前。
大規模災害、初期化<イニシャライズ>によって世界の三分の一は消滅し、人類の半数以上を失った。
国、家、仲間、家族、恋人を突然奪われ、残された人類は失われたものを取り戻す術を必死に探した。
そして、人類はある答えに辿り着いた。
この世に、運命は存在している。
そしてその運命は、記録として記されている。
しかし、人間が人間である限り、その記録にアクセスすることは許されない。
運命の記録とは、往古来今全ての行く末が記されている、此の世の循環システムに他ならないからだ。
ただし、人間が魔力を利用する事で触れる事の許される領域がある。
それが、運命の記録の複製<バックアップ>だ。
ただし、その複製がどこにあるのか、どんなものなのか、果たして目に見えるものなのかさえも判明
していない。
ただ、その複製さえあれば失われた世界の全てが元に戻り、尚且つ、記録されている世界の全てを書
き換える事も可能なのだ。
複製を手に入れる事が出来れば、運命の記録を上書きすることができる。
つまり事実上、世界の全てを自分の思うままにする事ができるのだ。
「世界の平和をとり戻る要となるもの―――――複製を、我々は邪な考えを持つ愚か者達の手に渡る
前に何としても見つけ出さなければならない」
バロックの瞳が、言葉の正義感に反してどこか怪しげにぎらりと光る。
それが噂に聞くひどく純粋過ぎる正義のせいなのか。
真意はわかりかねるが、バロックはその時ふっと柔らかく笑った。
「君には複製の手がかりを探し、それを奪おうとする敵と前線で戦ってもらうことになる。君の実力
を信じてはいるのだが、まあてっとり早く確かめてみようかね」
突然目の前で何かが弾ける音がする。
小さな白い煙と少々の焦げくさい匂いと共に、アリアの目の前に黒い表紙の厚い本が現れた。
そのまま落ちる前に、アリアは慌てて本を掴む。
「早速、任務だ」
王はどこか楽しげに笑った。
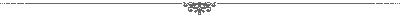
「大抵は移動時間中に、事前に渡されたこの資料に目を通して今回の任務の内容と目的を把握するの」
汽車に揺れながら、目の前に座るモニカからあらかたの説明を受けていた。
しかしそのほとんどをアリアは乗り物酔いの吐き気と眩暈で聞き流しており、もちろん資料に目を通
す余裕もなかった。
するとアリアの隣に座る、あちこちにはねた艶めく赤毛が特徴的な長身の男が、具合の悪そうなアリ
アの肩を思い切りたたいた。
「コイツ大丈夫かよ?なんかやばそうなんですけど」
彼の名前はオスカー。
彼もまた、モニカと同じく黒いコートを身に纏っている。
高い身長に、がっしりとした筋肉質な体つきから黒いコートを着ていなくとも相当な実力者のオーラ
を醸し出している。
今回の任務は、モニカとオスカーとカエンヌと一緒らしい。
汽車の一番上等な個室で、四人は任務の概要を話しあっていた。
「窓際変わりましょうか?」
にっこり微笑むカエンヌの顔を見る余裕もなく、そそくさと席を窓側に交替してもらい真っ青な顔を
風に晒す。
任務どころではないアリアを置いておいて、三人はとりあえず任務について話し始める。
「今回の目的地は、イーストシティよ。伝統ある街だけど、現在は完全に廃れてしまっているわ」
「昔は音楽で有名な街だったけどなあ」
「で、僕達の任務は何ですか?」
「一週間前、イーストシティへ向かった先遣隊からの連絡が途絶え、現在もなお消息不明」
「安否の確認と、原因の調査って事か・・・」
「もし敵にやられたのなら、そこに複製に関する手がかりがある可能性が高いと」
モニカは分厚い資料の本をパタンと閉じる。
そしておもむろに窓辺に目をやれば、アリアはだらりと窓の向こう側に頭と腕を垂らして既に戦闘不
能になっていた。
「あんた任務の前からその状態でどうすんのよ!」
モニカの一喝が汽車の個室に響き渡る。
ぴくり、とアリアの足が動くがどうやら限界らしい。
うぷっ、と危険なサインが聞こえたので三人はそれを合図に窓辺から目をそらす。
「オイオイ、この新入り大丈夫か?」
はっはっは、と何故かオスカーは笑う。
アリアは笑い事ではない、と言いたかったが、それとは違うものが口から出そうだったのでやめた。
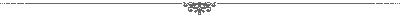
東の街、イーストシティ。
昔は音楽の都とまで言われた文明都市だったが、アリア達の目の前に広がる光景はそれとは程遠い木
枯らし吹く寂れた街だった。
昔なら街へ一歩踏み入れるたび音楽の一つや二つ聞こえてきたはずだが、今や人の声さえも聞こえな
い。
それどころか、大通りも人の姿さえ見えず、店らしき建物も全て閉じていた。
街を見回し、予想を上回る過疎化の現状にカエンヌは首を振った。
「人っ子ひとりいませんね」
「先遣隊どころか、街の人さえいないなんて、おかしいわね」
「とりあえず、探そうぜ」
オスカーが先頭を切って歩きだす。
この街の大通りであるはずの道に、四人の足音だけが静かに響く。
風の音が、妙に耳につく程他には物音が無い。
おかしい。
この静けさは、異常だ。
「ちょっと・・・・気配さえ感じないんだけど」
「そこらへんの民家にちょっくら入ってみるか?」
オスカーが、強く民家の扉を叩く。
ノックの音は大通りに虚しく響きわたるだけだった。
「・・・・入るぞ」
ドアノブを捻るが、鍵が閉まっていた。
それがわかるとオスカーはためらいもなく、すぐにドアを蹴り飛ばした。
「ちょっとオスカー、やり過ぎよ」
「魔法を使うまでもないだろ」
ははっと、こんな状況でもオスカーはおおらかに笑う。
ドアを踏みつけて民家の中へ入ると、その光景を見て四人とも怪訝そうな表情をした。
昼間なのに電気がついている。
机の上には片付けられていない食べ残されたシチューとかじりかけのパン。
「まるでさっきまで誰かが生活していたような・・・」
「いや・・・・さっき、というのは考えにくい」
珍しくアリアが口を開いたので、三人は同時にアリアの方を振り向く。
さっきよりは随分顔色がよくなったアリアは、そっと机の上の食器に手を触れる。
「さっき、にしては昼間に電気はおかしいし、料理も冷たい」
「最低でも十二時間は経ってるって事ね」
「でも血痕や荒らされた形跡が無い事から、奴らの仕業ではないみたいですね」
「奴ら?」
アリアが眉をひそめると、三人が互いの顔を見合わせる。
モニカが説明しようとしたのを何故か遮って、オスカーが説明してくれた。
「陰影・・・複製を狙う、クレイシアの敵対組織だ。その存在は公になってねえから入ったばかりの
アリアは知らないと思うけど」
「この先、陰影と対峙する事があるかもしれないけど・・・」
モニカの言葉の先を待つが、何故かモニカはそこで言葉を切ったまま何も言わない。
不思議そうに首を傾げるが、オスカーもカエンヌもそれについて特に言及しない。
まあいいか、とそこまで敵の組織に興味の無いアリアはモニカから目を反らす。
何故か黙り込むモニカを見て、ふむ、とカエンヌは顎に触れる。
それが何故かはわからないが、癖なのだろうか、とカエンヌの方を見ていると、カエンヌの肩越しに
全身鏡が見えた。
おもむろに全身鏡に目をやったが、その瞬間アリアの全身に悪寒が走った。
「あッ」
アリアは思わず声をあげた。
その声に、その場にいた全員が瞬時にアリアの方を振り向く。
硬直したまま動かないアリアを、無言で三人が見つめる。
しばらくの沈黙の後、ふっとアリアが身体の力を抜いたのを見てモニカがアリアに歩み寄る。
「何?どうしたの?」
「視線を感じた・・・」
「どこから?」
「・・・・・いや」
気のせいだったのか。
鏡越しにだったのか、と思って背後を振り返るがそこには壁しかなく、窓さえ無い。
今のは一体何だったのか。
アリアは神経を張り詰めるが、もう何も感じなかった。
何かある。
この街には、何かがある。
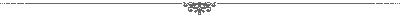
銀色の扉の向こう
二つの月
天使の祈りのような光を
どうかこちらの世界まで
届けておくれ
あなたの対である私の元へ
その光を届けておくれ
どうやらこれは、この街に伝わる民謡らしい。
アリアは壁にかかっている歌詞を眺める。
調べたところ、街の民家のほとんどにこの歌詞が額縁に入って飾られていた。
よほど街の人々に親しまれている唄のようだ。
この歌の中に何かヒントが隠されているか、とも思ったがそれほど重要な単語も見当たらないのであ
きらめた。
その民家の扉を閉める。
外に出ると、木枯らしが吹く音しか聞こえない。
今は、各自四方に別れて別々に捜索している。
アリアはとりあえず民家を一軒一軒あたっていたのだが、どこも状況はさほど変わらなかった。
食べかけの料理、積まれた洗濯物、付けっぱなしのラジオ。
どう考えても、失踪するような状況ではない。
第三者による何か、と思った方がいい。
「・・・・血?」
近くの路地で、地面にふと見つけた小さな黒い点。
それは感覚がだんだん狭くなりながら、どこかへと続いていた。
誰の血だろう。
乾いている事から、モニカ達のものではない事はあきらかだった。
とすると、街の人々か先遣隊か。
他の誰かか、陰影か。
アリアは早足でその血を辿る。
路地を幾度か曲がり、徐々に細くなっていく路地が、急にひらけた場所に出た。
アリアは辺りを見渡す。
そこは広場のような、四隅に木が一本ずつ立っている他は何も無い小さな場所だった。
木々も無い、四方を大きな建物に囲まれた、正方形の形をしたまるで意図的に隠されているような場
所。
怪しい。
アリアは広場の中央に立つ。
四本の木にぶらさがっているものを見て驚くでもなく、ただ顔をしかめる。
死体。
おそらくは先遣隊。
だが、白いコートを着ていない。
ふと見ると、白いコートは切り刻まれて木の根元にあった。
あの頑丈な白いコートを切り刻むほどの力を持つと言う事は、敵は魔導師。
陰影という奴か?
死体を見ると、あきらかな他殺。
だがおかしい。
路地で殺され、ここまで連れてこられたのか?
それとも路地で敵と遭遇して、怪我をしてここまで追い込まれたのか?
どちらにしろ、あれは一人分の血だった。
ここにある死体は四つ。
「あちゃ、見つかっちった」
突然聞こえたその声に、素早く辺りを見渡す。
密かに戦闘態勢に入ったが、驚く程敵は目の前にいた。
「どーも。初めまして。見慣れない顔っすね?」
黒いスーツを着た白髪の男が、笑った。
| 







